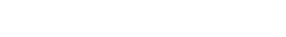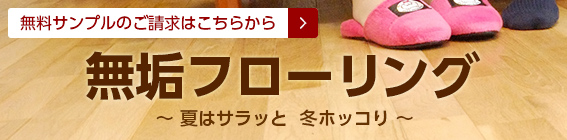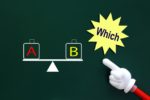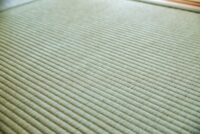無垢フローリングのお手入れ方法をご紹介!べたつきがある時は?
アトピッコハウスの事務所がある鎌倉は湿度が高い地域です。
梅雨や夏場の湿度が高くなる時期は、顔や体がベタベタして不快です。
家の中も同じで、フローリングがベタベタして、
不快だと感じることはありませんか?
べたつく床の原因は何か?
べたつきを取るにはどうしたら良いか?
無垢フローリングと合板フローリングでべたつきに違いはあるのか?
不快な季節も快適に過ごせるよう、
フローリングのべたつき対策についてご紹介します。
目次
フローリングのべたつきの原因は?
自然素材の内装材専門メーカー、アトピッコハウスの成川です。

べたつきの感じ方は、フローリングの種類や塗装によっても変わりますが、
べたつきの大きな原因は、足裏の皮脂などの油分です。
夏は暑くて、裸足で過ごす時間が増えます。
髪の毛やホコリはフローリングワイパーで取り除けても、
皮脂汚れはなかなか除去できません。
べたつく汚れは足裏の皮脂だけでなく、
食事や調理で発生する飛び跳ねた油にも原因があります。
家の中で焼き肉をやったり、
普段の調理をするだけで部屋中に油が飛び散って、
ベタベタを超えてヌルヌルになってしまった経験はないですか?
そうした、皮脂や食べ物の脂汚れが蓄積したところに、
梅雨時期の湿度がプラスされ、ベタベタがひどくなるのです。
フローリングの中でもべたつかないのは、無垢フローリング!
フローリングのべたつきは、合板フローリングや塩ビのクッションフロアを張った床で感じた経験があるのではないでしょうか?
天然木の無垢フローリングは、保温性と調湿性能に優れた天然木を加工した床材のため、夏にはサラっと過ごせ、冬はヒヤッと感じにくいのが特徴です。
無垢材とはどういうもの?
無垢材とは1本の木を伐り出して作った木材のことです。
ナラや桧、スギといった木材が人気で、家具やフローリングにもよく使われています。
無垢材は使うほどに独特な風合いが増していくのが魅力の1つで、
年月が経過する中で色合いが深くなる無垢材は、味があり愛着が沸いてくるでしょう。
無垢材は天然木本来の美しさを楽しめるだけでなく、夏の湿度が高い時期は木材が湿度を吸収し、冬の乾燥する時期は木材から水分が放出される「調湿機能」を活かせるので、フローリングの選択肢としてはメリットが多いのです。
無垢フローリングはお手入れが大変?
フローリングの選択肢として無垢フローリングにしたいと思った時に、
次に気になるのは「無垢フローリングはお手入れが大変なのでは?」
ということではないでしょうか?
結論から言うと、毎日手間をかけてお手入れする必要はありません。
確かに集成材である合板フローリングよりデリケートな木材ではありますが、
特徴や注意点を知り、気を付けてお手入れをすればそれほど大変ではありません。
後ほど詳しく説明をしますが、無垢フローリングには自然塗装やUV・ウレタン塗装といった塗装方法があります。
UV・ウレタン塗装なら静電気が発生するのでホコリが付きやすいですが、
自然塗装や無塗装なら静電気が発生しないので、それほどホコリも目立ちません。
窓を開けて、乾いたフローリングモップやホウキで掃けば十分です。
しかし水分を多く含んだ布で拭いたり強い薬品を使ったりすれば、逆にシミになってしまったりする事があります。
そのため、仕上げの塗装にもよりますが、水分を使わない「乾拭き」を基本として、しつこい汚れには固く絞った雑巾やクロスを使う方法がおすすめです。
お手入れがしやすい無垢フローリングは?
お手入れがしやすい無垢フローリングにするなら硬めの樹種がおすすめです。
「簡単にお手入れができるものがいい」
「濡れた雑巾でも大丈夫な、丈夫な無垢フローリングがいい」
という方はある程度硬さのある木材で作られた無垢材がおすすめです。
硬めの樹種
次に挙げる樹種は他の樹種と比べて硬度が高く、傷がつきづらいのでお手入れしやすいです。
・カエデ
・カバ材
・アッシュ
・チェスナット
ただし、硬さのある木材は傷や凹みが生じた時に補修をしにくいという特徴があることも覚えておきましょう。
浮造(うづくり)仕上げ
無垢フローリングの「うづくり」という加工方法をご存じでしょうか?
「うづくり」は木の柔らかい部分に凹みをつくり、年輪を凹凸に仕上げる方法です。
柔らかい木ならではの、仕上げ方法です。

うづくりの古材
うづくり仕上げにする場合のメリットは、傷が目立たず、自然な踏み心地を実感できるところです。
デメリットは、深彫りにしすぎると体重をかけた際に痛いと感じることもありますが、ほぼデメリットはないと思っていいでしょう。
塗装方法によっては、無垢フローリングもべたつきを感じる
自然塗装、UVウレタン塗装など無垢フローリングは、塗装の種類を選ぶことができます。
色の濃い液体(コーヒー、しょうゆなど)を無垢フローリングにこぼした場合、
無塗装や自然塗料ほど、シミになりやすくなります。
合板のフローリングやウレタン塗装の無垢フローリングはべたつきを感じられやすいので、
無垢床でべたつきを感じたくないのなら、塗装は最小限に抑えたいところです。
長年使っているフローリングのワックスは、
だんだんはげてきているはず。

ワックスがはがれて劣化したフローリング
劣化したワックスはベタつきやすくなるうえ、表面のコーティングがはがれてきているので、
フローリング表面に汚れがつきやすくなるなど影響があります。
ワックスを塗って、再度コーティングして修復してあげることが必要ですが、ワックスは床材に適した商品を選び、塗布量に気を付けましょう。多く塗布すると、ベタベタ感が増すので注意が必要です。
アトピッコハウスの無垢フローリング「ごろ寝フローリング」は、自然塗装品、UVウレタン塗装、無塗装の商品をご用意しています。
▶べたつきが気にならない「ごろ寝フローリング」の詳細は、こちら
無垢フローリングのお手入れ方法を塗装や仕上げごとに解説
先にもお伝えしましたが、基本的なお手入れは乾拭きで、汚れがついている場合は雑巾を水で濡らして硬く絞って拭きましょう。
無垢フローリングのお手入れの仕方は仕上げの塗料の種類によって変わるので、正しい知識が必要です。
ここでは、無垢フローリングの塗装ごとのお手入れ方法を解説していきます。
UV・ウレタン塗装の無垢フローリング
UV・ウレタン塗装は、ウレタン系の塗料で無垢材の表面をコーティングする方法です。
コーティングによって強いツヤが出るので、高級感や重厚感があります。
最近ではウレタン塗装より塗膜が薄く仕上がる、「UVウレタン塗装」の人気が高まっています。
UV・ウレタン塗装は触ると木本来の凸凹を感じずツルツルしているのが特徴です。
耐水性が高く、水分のある汚れが染み込みにくいというメリットがあります。
コーヒーやお醤油といった着色性のある水分が落ちても浸透しないので、汚れが残りにくい点が魅力です。
日常のお手入れの方法は以下の手順で行いましょう。
・表面のゴミやホコリを掃除機や箒で掃除する
・雑巾で乾拭き
紙やすりやサンドペーパーは表面がくすんでしまうため使わないでください。
定期的なメンテナンスとして、1~2年ごとにウレタン塗装に適したワックスを塗布すると長持ちします。
自然塗装(オイル塗装)の無垢フローリング
自然のオイルを無垢材の表面に染み込ませて着色しています。
自然塗装は「着色」という意味合いに限らず、木材の保護としても使われているのです。
木の表面に塗料のオイルを染み込ませているため木の呼吸を妨げず、木本来が持っている断熱性や調湿性といった機能を損なわない点が魅力です。
そのため、無垢材の中で一番人気の塗装方法となっています。
オイル塗装はUV・ウレタン塗装よりも自然なツヤがありしっとりしていて、触ると木本来の凹凸を感じられます。
オイル塗装の仕上げはウレタン塗装と比べると、静電気が発生しにくいためホコリが床にくっつくことが少ないです。
窓を開けて風邪通しをよくするだけでもある程度ホコリを取り除くことができます。
それでもホコリが気になる場合は箒やフロアワイパーでホコリを取り除きましょう。
オイル塗装の場合は傷ができた時やシミができた時に紙やすりやサンドペーパーを使用して修復した後、削れた箇所には改めてオイルを塗布しましょう。
無塗装の無垢フローリング
表面に何も塗っていない状態を無塗装といいます。
もっとも無垢材の魅力を感じる方法ではありますが、あまり無塗装のままで無垢フローリングにすることはおすすめしません。
表面が一切塗装されていない状態だと、無垢材はとても汚れやすく傷つきやすいです。
たとえばコーヒーやお醤油をこぼせばすぐに染み込んでしまいますし、裸足で歩けば黒ずみが目立ってしまいます。
お手入れは乾拭きで、汚れはその場ですぐに拭き取りましょう。
こびりついている場合は雑巾を水で濡らして硬く絞って拭き、乾拭きし水分を乾燥させましょう。
無垢フローリングに付着したべたつき汚れの掃除方法
食事の際に、食べこぼしで床が汚れる場合があります。
染みたり、ベタベタした汚れも多いですよね。
無垢フローリングの塗装ごとの基本のお手入れ方法は分かりましたが、
今度はシミやべたつき汚れの場合の具体的な掃除方法についてみてみましょう。

◆自然塗装(オイル塗装)の場合
コーヒーやお醤油など濃い液体をこぼした場合、いつまでも放置せず手早く拭き取れば大きなシミになりません。べたつき汚れが残っていたら、メラミンスポンジで優しくこすってみましょう。
◆UV・ウレタン塗装の場合
コーヒーやお醤油など濃い液体をこぼした場合、ウレタン塗装の場合は内部にしみ込みにくいので、乾いた布で拭き取りましょう。シミになりにくいし変色しにくいですが、粘着質の水分をこぼしてべたつく場合は、薄めた中性洗剤で硬く絞った雑巾で磨くと良いでしょう。
◆無塗装の場合
表面に何も塗っていない無塗装の無垢材は、汚れや傷がつきやすいです。
コーヒーやお醤油をこぼせばすぐに染み込んでしまいますし、黒ずみが目立ってしまいます。自然塗装品と同様に手早く拭き取れば問題ないです。
べたつき汚れは固く絞った雑巾で拭き取り、乾拭きし乾燥させましょう。
ハウスクリーナーこめっとさん

アトピッコハウスのクリーナー「こめっとさん」は、
米ぬかなどお米由来の成分で作られています。
無垢フローリングのメンテナンスでお悩みの方は、
塗装方法に限らず使えます。合板フローリングでも、ビニールクロスでも
お部屋中に使えるし、ワックス効果もあり、便利な商品です。
▶無垢フローリングにも使える米ぬか由来の優しいクリーナー「こめっとさん」の情報は、こちらからご確認ください。
無垢フローリングを長持ちさせるためのポイント
無垢フローリングを末永く愛用するために心がけておきたいポイントと具体的なお手入れを紹介します。
基本の手入れは乾拭きだけ!
先ほども解説しましたが、普段のお手入れは乾拭きだけでOKです。
乾いた雑巾やモップ、フローリングワイパーでホコリを取り除きましょう。
1か月に1回、年に1回など大掃除、長期的なメンテナンスの方法は次でご紹介します。
1か月~3か月ごとに1回水拭きを!
汚れがこびりついている箇所は、固く絞った雑巾で水拭きしましょう。
その後、乾拭きをするなど乾燥させましょう。
また、目地の隙間に入り込んだ汚れは、つまようじなどを使って取り除いていきます。
傷がついてしまったら、自然塗装の場合はサンドペーパーで擦って補修できますが、擦った後はもう一度塗料(オイル)を塗りましょう。
大掃除を1年に1回しよう!
箒や掃除機でゴミを取り除き、リビング、廊下などよく歩く部分を中心にワックスを塗布しましょう。
ワックスは塗装剤との相性があるので、必ずリフォーム会社に塗装剤のメーカーを聞いたり、おすすめのワックス材を確認したりしてください。
合わないワックスを使用したり、あまり頻繁にやるとベタつくので、年に1回程度大掃除の時で構いません。
塗装が痛んできたら再塗装をしよう!
撥水性が落ち、塗装が痛んできたと感じられたタイミングで塗料を再度塗りましょう。
塗装前にフローリングについたホコリをしっかりと取り除いてから塗るとムラが少なく仕上がります。
使用する塗料は元のものと同じものかなど、使用できるものかどうかを確認しましょう。
またこの時「ささくれ」があるのであれば、補修をしましょう。
表面をコーティングしていない自然塗装の場合、ささくれが起こりやすくなります。
逆にUV、ウレタン塗装の場合はささくれは起こりにくいでしょう。
自然塗装の無垢フローリングで「ちょっと気になる」という軽度のささくれなら、やすりで軽く磨くだけで良いです。
ただし、いきなり目の粗いやすりは使わず、200番~300番台の中程度のやすりを使いましょう。
擦る時は、かならず木目と同じ方向にかけるようにします。
「足に刺さったら大変だな」という中程度のささくれなら、やすりをかける前にささくれをカッターなどで削り取ります。
やすりだけで補修しようとすると、凹みが大きくなって目立ってしまうためです。
やすりをかけた後は、その部分にワックスやオイルを塗って木肌を保護してあげましょう。
重要!無垢フローリングのお手入れに使えるものと使えないもの
無垢フローリングのお手入れには適しているものと適していないものがあります。
使えるものを改めて確認しましょう。
先述した通り、基本的なお手入れは乾拭きだけで問題ありませんので、ホコリを取り除くことができれば雑巾、モップ、フローリングワイパーなど、ご自身が使いやすいものを使ってください。
無垢フローリングに傷がついてしまった場合はサンドペーパー・紙やすりで補修しましょう。
ただし、補修した場所を再度塗装する必要があるので注意してください。
ウレタン塗装の場合は再塗装が素人の手では難しいので、サンドペーパーは使わないようにしましょう。
また、部分的な傷の補修では蒸気も効果的ですが、無垢フローリング全体にスチームクリーナーを使うことは避けましょう。
高温の蒸気で汚れを浮かせるスチームクリーナーは、無垢フローリングを傷めてしまうからです。
自然塗装や無塗装の無垢フローリングは、木が呼吸しているため調湿効果もあります。
そんな無垢材に高温のスチームクリーナーをかけると、木が水分を吸って一気に膨張してしまいます。
その結果、反ったりひび割れたりする原因になりかねません。
また、UV・ウレタン塗装の無垢材は耐水性がありますが、塗装の劣化具合や種類によっては高温に耐えられず白濁する可能性もあります。
フローリングのべたつきが気になる時は、固く絞った雑巾やクロスで優しく拭き、最後に乾拭きをして水分を残さないようにしましょう。
次に洗剤についてです。
無垢材はデリケートなので安易に洗剤を使ってはいけません。
強い酸性の洗剤をはじめ、化学薬品を使った洗剤は避けるようにしましょう。
木が化学薬品を吸収して色ムラができたり、黒ずみが目立ったりします。
無垢フローリングのお手入れでどうしても洗剤を使いたい時は、薄めた中性洗剤や無垢材専用の優しい洗剤がおすすめです。
無垢フローリングはべたつきがないし、メンテナンスも簡単
湿気が高い季節に特に気になるベタつく感触は、
無垢フローリングであれば感じません。
大変だと思われがちな、
無垢フローリングのメンテナンスも
実は簡単なので、忙しい子育て世代にもおすすめです。
ここまでお伝えしてきた通り、普段は、フローリングワイパーや掃除機で。

ベタつきが残る汚れを付着してしまったら、ゴシゴシと水拭きはせず、
無垢フローリング用の専用クリーナーでお掃除し、汚れをすばやくとるようにしましょう。
アトピッコハウスのクリーナー「こめっとさん」は希釈して薄めた液をスプレーして、フローリングワイパーで拭き取るだけなので、簡単にお手入れができます。
小さな傷は、塗装をしていない無垢床であればサンドペーパーでとることができますし、
アイロンの熱の蒸気で無垢床の凹みを補修することもできます。
湿ったタオルを凹んだ場所に置き、低温設定でアイロン(30秒目安)をあてる方法です。
これは、本物の木だからこそできる補修方法です。
▶アトピッコハウスの無垢材「ごろ寝フローリング」のメンテナンス方法はこちらからご確認ください。
まとめ
湿気が多い時期に特にベタつきがちな床で、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
無垢フローリングにすることで、夏はサラっと、冬はあたたかく、快適に過ごせるはずです。
無垢フローリングの塗装ごとの特徴、基本のお手入れ方法、汚れなどからくるべたつきの掃除方法などを知ることで、
長く無垢の風合いを感じながら暮らせます。
アトピッコハウスの無垢材「ごろ寝フローリング」は、
アカシア、パイン、カバ、桧など使いやすい色合いから、
重厚で高級感のあるウォルナットやチェリーなど、幅広いラインナップがあります。
また、無垢フローリングのメンテナンス方法でお悩みの場合も、ぜひご相談ください。
▶バリエーション豊富な無垢フローリング「ごろ寝フローリング」の詳細はこちら
よくあるご質問
フローリングのベタベタを取り除くには?
湿気が原因でベタベタする場合には洗剤などは特に使用せず、水拭きをするだけで落とせることが多いです。
固く絞った雑巾で拭き取り、乾拭きをして水分を拭き取りましょう、
皮脂汚れが混ざっていても、2回程度水拭きすればほとんど落とせます。
無垢フローリングの欠点は何ですか?
傷やシミなどの汚れが付きやすいというデメリットがあります。
無垢材の中でもスギやパインなどの針葉樹は特に柔らかいので、物を落とすと凹んでしまうことも。
しかし、無垢材は凹みに水分を与えて復元させたり、傷の部分を削ったりして、ある程度の修復が可能です。
無垢床にウタマロは使えますか?
無垢フローリングは、素材の中に水分が吸収されてしまうので、ウタマロの使用は避けましょう。
無垢床は水拭きはだめですか?
毎日のお掃除では、ウェットなクイックルワイパーや、水拭きは雑巾に含まれる水分が無垢床に浸透して変形などを起こす可能性があるので、極力控えたほうがよいでしょう。
オイルやワックスで保護していても、無垢はどうしても水を吸い込みやすい素材です。
ただし、汚れが目立つときや、食べ物をこぼしてしまったときなどは、固く絞った雑巾で拭き取ることはO Kです。
そのあと乾拭きをして水分を取り除きましょう。
無料で、資料・サンプル差し上げます
アトピッコハウスは、無垢・珪藻土・漆喰・クロス・畳など
オリジナルの自然素材内装材を、製造販売する会社です。