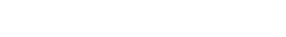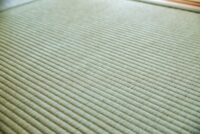畳の敷き方のルール!畳の基本の敷き方をお伝えします。
畳の敷き方はご存じですか?実は畳の敷き方には決まったルールやパターンがあります。日本人にとってなじみのある畳ですが、その敷き方まで理解している方は意外と少ないかもしれません。畳を敷く際のルールや正しい敷き方、和室の部屋の広さごとの畳の敷き方の紹介と、注意したいポイントをお伝えします。
アトピッコハウスの「ほんものたたみ」は宮城県産のワラ床と熊本県産のイグサでできた純国産の畳です。

自然素材の内装材専門メーカー、アトピッコハウスの日比野です。
畳の敷き方のルールは江戸時代に生まれました。畳の敷き方には、祝儀敷きと不祝儀敷きという2つの種類があります。昔は行事によって畳を敷き替える慣習がありました。その時々の行事によって2種類の畳の敷き方の方法が生まれたと言われています。
一般的な住宅に畳を敷く場合、「畳の合わせる目が十字にならないようにする」というルールがあります。その為には、それぞれの畳の四隅が一か所に集まらないように工夫をする必要があります。
江戸時代よりこの十字にならない敷き方は縁起が良いとされてきました。このルールに乗っ取った敷き方を祝儀敷き、ルールに反している敷き方を不祝儀敷きと言います。
目次
祝儀敷き(しゅくぎじき)
祝儀敷きとは隣り合う畳のラインが十字にならないようにする敷き方です。一般的な和室の畳の部屋に用いられてきました。畳を同じ方向に二列並べると、合わせ目に十字ができてしまいます。それを防ぐために祝儀敷きではわざと違う方向に畳を敷き、縁起が良いものとされ、婚礼などのお祝い事では必ずこの祝儀敷きが用いられてきました。
結婚式や葬式などを家ですることも少なくなった現代、個人宅の和室は祝儀敷きになっていることが一般的になりました。また、祝儀敷きは「枕敷き」「回り敷き」と呼ばれることもあります。
不祝儀敷き(ふしゅくぎじき)
不祝儀敷きとは畳の目が十字になる敷き方です。祝儀敷きがお祝いの場で用いられる一方、不祝儀敷きは葬儀などの際に使われてきた敷き方です。法要などを行う神社仏閣では不祝儀敷きが主流となっています。
すなわち不祝儀敷きは祝儀敷きと違って、一般住宅ではあまり見ない畳の敷き方といえます。昔は葬儀などのときに畳を不祝儀敷きの配置に敷き直していましたが、現代ではその風習はなくなりました。不祝儀敷きは「四ツ井敷き」とも呼ばれています。
アトピッコハウスのほんものたたみは熊本県産の減農薬イグサを使っています。
部屋のサイズに合わせた畳の敷き方

それでは、実際の畳の敷き方についてご紹介します。それぞれの和室の広さに合わせたサイズに合わせたものを参考にしてください。
3畳の畳の敷き方
3畳の場合、まず部屋の一番奥に横向きで畳を敷きます。そしてその手前に縦向きで2枚畳を敷くと祝儀敷きになります。すべて横向きで1列に並べると不祝儀敷きになります。
4畳半の畳の敷き方
4畳半の場合、まず部屋の一番奥に横向きで敷きます。そして左側に縦向きで1枚敷き、空いたスペースに横向きで2枚敷くと祝儀敷きになります。この時に手前の3枚を縦向きに並べると不祝儀敷きになります。
6畳の畳の敷き方
6畳の場合、まず部屋の一番奥に畳を横向きで2枚敷きます。そして左右に1枚ずつ縦向きの畳を敷きます。最後に真ん中に横向きで2枚上下に敷くと祝儀敷き、また、6枚すべての畳を並列に横向きで並べると不祝儀敷になります。
8畳の畳の敷き方
8畳の場合、まず6畳の祝儀敷きと同じ敷き方をします。そして手前に横向きで畳を2枚敷けば完成です。8枚の畳を縦向きで並べると不祝儀敷きになります。
10畳の畳の敷き方
10畳の場合、まず8畳の祝儀敷きと同じ敷き方をします。そして右側に空いたスペースに、縦向きに2枚の畳を並べます。10枚の畳をすべて縦に敷くと不祝儀敷きになります。
12畳の畳の敷き方
12畳の場合、まず10畳の祝儀敷きと同じ敷き方をします。12畳の場合左側に畳2枚を縦に敷き詰めるため、右側に詰めるように配置します。不祝儀敷きは部屋の奥側に横向きで畳を3枚敷き、その手前に縦に6枚敷きます。最後に一番手前側に横向きで3枚の畳を敷きます。
アトピッコハウスの「ほんものたたみ」にも、縁ありと、縁無しの両方の畳があります。
畳の敷き方 その他に気を付けたいルール

祝儀敷き・不祝儀敷き以外にも、畳の敷き方では気を付けるべき細かなルールが存在します。畳の敷き方に関する伝統的なルールについて紹介します。
鬼門半畳は避ける
四畳半の部屋の場合、半畳の畳を使用します。その場合、位置に気を付けなくてはなりません。半畳の配置場所は鬼が出入りする方角といわれる「鬼門(北東)」を避けるというルールがあります。
古来より鬼門は不吉な角度とされており、様々な場面で避けられてきました。家の間取りを決める時も、鬼門を考慮した配置になるよう気を配ります。和室に半畳の畳を配置する際は鬼門を避けるようにしましょう。
四畳半左回りで敷くと「切腹の間」に
四畳半の部屋でもう一つ注意しなければならないのが「切腹の間」と呼ばれる敷き方です。鬼門半畳を避けると、真ん中に半畳を敷くレイアウトが考えられます。しかし、半畳を中心にして他の畳が左回りになるように敷くと、「切腹の間」という形状になってしまいます。
切腹の間とは、武士たちが切腹する際に用いた敷き方です。部屋の中心の一枚に切腹する武士が座り、切腹後にその一枚を交換したといわれています。現代でも「縁起が悪い」という理由で、切腹の間と同じ敷き方は敬遠されています。もし、真ん中に半畳の畳を敷く場合は畳が右回りになるように配置します。
入口と床の間の畳の敷き方
和室に床の間がある場合、床の間と平行に畳を敷きます。床の間に対して畳の縁が直角になる敷き方は「床刺し」と呼ばれ、この「床刺し」も「切腹の間」同様、武士が切腹する際に使った形といわれ避けられてきました。
また、お客様を和室に通す際は床の間の前が上座になります。床刺しに座るとヘリを踏んでしまうことになり、このように畳を敷くと、お客様を畳の継ぎ目に座らせることになってしまいます。
畳の目が合っていないため後ずさりもしにくく、お客様にとっては居心地の悪い場所となってしまいます。この2つの理由から、床刺しは避けるべき畳の敷き方とされています。また、入り口から入る時に畳の目が進行方向になるようにするため、入り口と畳は平行に敷くようにします。
茶室の畳の敷き方
茶室や掘りごたつのある4畳半の和室で半畳を中央に配置する場合は畳を右回りに配置します。
旅館の大広間は不祝儀敷き
旅館の大広間では不祝儀敷きが用いられていることがあります。これは、大勢の方が同じ向きで利用することが多いからです。主に食膳を並べて宴の場に利用されることから、不祝儀敷きですべて同じ方向で畳が敷かれていれば、畳が傷みにくくメンテナンスもしやすくなります。
また、お客様の並びと畳の向きが同じ方向だと、見栄えも良く、作業もしやすいという事情もあります。その他にも小学校や公民館の和室も祝儀敷きの部屋が多くなっています。
アトピッコハウスは昔ながらの「ほんものたたみ」の販売をしていますが、畳工事も承っています。お気軽に畳の悩みをご相談ください。お見積りも可能です。
まとめ

あまり知られていないかもしれませんが、畳の敷き方には古くからの伝統やルールがあり、和室には細かな決まりごとが少なくありません。
現代では縁起やしきたりをあまり気にしないかもしれません。ですが正しい敷き方を知っておくことは日本の文化を理解する上で、とても重要です。不祝儀敷きや鬼門、切腹の間などにまつわる「縁起」という考え方は、日本の住宅において大切にされています。ぜひルールに則った敷き方で、気持ちよく過ごしてください。
よくある質問
畳を敷くときのルールは?
「畳の合わせ目が十字にならない」事が、畳の敷き方のルールです。この敷き方は江戸時代より縁起が良いとされ、現在でも名残が残っています。そして、畳の合わせ目が十字になっていない敷き方を「祝儀敷き」、畳の合わせ目が十字になっている敷き方を「不祝儀敷き」と呼びます。
畳の敷き方の順番は?
畳の敷き方は、周囲の壁から順番に敷きます。最後の畳を入れるときは、2枚の畳の角を山のように合わせて上から抑えて敷きます。畳の大きさや部屋の広さ、敷く場所によって、敷き方は異なります。
畳6帖の敷き方は?
6畳の場合は、部屋に向かって奥側に2枚の畳を横向きに並べます。 そしてその下に縦向きの畳を1枚、横向きで上下並べた畳を2枚、さらに縦向きの畳を1枚配置します。
畳の目の向きは?
畳縁と垂直の方向を畳の目の向きといいます。 最近は畳縁のない半帖タイプの置き畳・ユニット畳も多くありますが、基本的な考え方は変わりません。
無料で資料・サンプルを差し上げます
アトピッコハウスは、無垢、珪藻土、漆喰、クロス、畳など
オリジナルの自然素材内装材を、製造販売する会社です。